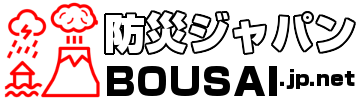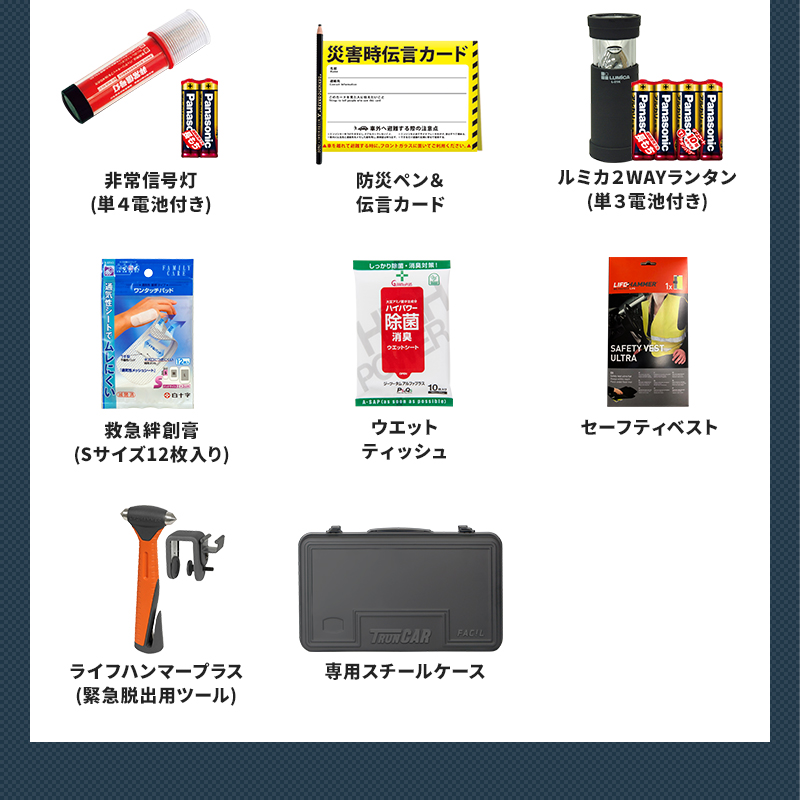地震や台風など、多くの災害に頻繁に被害にあう我らの国、日本では常に防災を意識した生活を自然と営むように教育されています。
幼少のころから教育機関で災害の恐ろしさを体験したり学んだり、平時の生活でも身近で非常食や家具転倒防止アイテムなどを使った災害対策をしています。
そんな社会で生きてきたため、大人になっても非常食への関心が自然に生まれたり企業によるより良い非常食の開発なども進められています。
非常食、どれくらい用意する?
皆さんは非常食を用意されていますでしょうか? 用意されている方はどれくらいの量を用意されていますでしょうか?
実は、非常食の個人による備蓄は政府が推奨する防災行動となっているんです。

上の内閣公式HPの「災害に対するご家庭での備え」には以下のように書かれています。
食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例(人数分用意しましょう)
飲料水 3日分(1人1日3リットルが目安)
非常食 3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パンなど
トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ、ろうそく・カセットコンロ など※ 大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。
最低でも3日分、利用は1週間とされています。この日数はざっくり決めたものではなく、日本で起きた今までの災害による被災者のデータから導き出された確かな情報です。
基本的に災害時には被災地に支援物資が届けられます。その中にも勿論食料は含まれています。が、これらの支援物資が届くまでどうしても時間がかかるのです。
被災者の自治体における数の把握と仕分け、物流会社への発送手続きや場合によっては自衛隊の派遣によって運ばれますが、何をするにも手続きが必要ですし、確認、仕分け、梱包、荷詰め作業を経てようやく配送開始となるのでどうしても最低限の時間が必要なんです。
その日数が最短でも3日、災害が大きければ倒木や地割れ、洪水などによる交通インフラ機能の停止から復帰まで更に時間がかかります。その最悪のケースも想定して理想は1週間、とされているのです。
企業の課題は大きい
また、非常食を含む防災用品の備蓄は一般家庭だけでなく企業にも求められています。これは倫理的なものではなく、法律的なもので、企業は安全配慮義務が義務付けられており、被雇用者や顧客の安全を守る配慮を行う義務があるとされており、実際に最高裁で判決が出た事例もあります。
企業が災害を想定して防災用品を用意したり災害対策を講じるのは法的責任があるのです。また、企業防災のガイドラインも政府によって設けられています。
ガイドラインに沿わずに何も用意しなかった場合でも何かしらの罰則がある訳ではありませんが、用意しなかったことで被雇用者や顧客に被害が生じた場合は責任を負われる可能性があります。
帰宅難民問題
たとえば都心部では出勤中の災害により交通インフラが機能を停止し、帰宅が出来ない方が多く見られた事例があります。
大災害級になるとさらに多くの帰宅難民が増える恐れがありますが、公共施設等で受け入れるのは無理があるほど、都心部で働く方は多く存在します。
そのため、企業には出来る限り被雇用者や顧客の一時受け入れ先になってもらいたい、というのが政府の本音のようです。
非常食7年保存クッキー50食セット

こちらはそんな企業の方にお勧めの非常食50食分のセットです。軽食タイプで水も不要なので帰宅難民用の備蓄に最適です。
また、パウチに入っているので大量のゴミを出さずに済みますし、コンパクトで保管の場所も取らないメリットがあります。

多少の量の少なさはありますが、カロリーはある程度摂取できますので問題ないでしょう。箱に入れてあるのでそのまま備蓄出来るのも嬉しいですね。